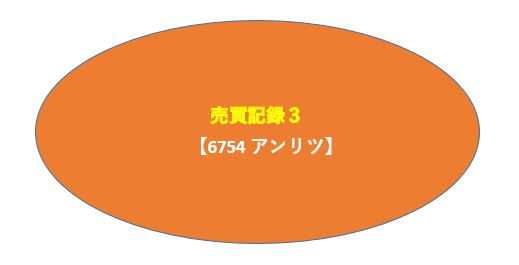
こんにちは、あつろうです。
このブログは、「これから株式投資を始めたいと思っている人」、
投資初心者で、「これから投資家として成長したい人」、に向けて、
【株式投資初心者が利益を上げるまで】を目的として、
株式投資に役に立つ知識や、ノウハウを発信していきます。
今回のテーマ【実売記録3】6754 アンリツ です。
実際に売買した銘柄を公開し、購入根拠や結果分析を行っていきます。
具体的には、以下のポイントに沿って、購入~売却までの流れを解説していきたいと思います。
・アンリツ 何やってる企業?
・購入根拠
・売買結果
手法や考え方など、参考にしていただければと思います。
・アンリツとは

通信系測定器の有力企業 全体売上の70%が測定事業
デジタル通信・IPネットワーク用測定器、光通信用測定器、移動通信用測定器、RF・マイクロ波・ミリ波など
測定機器の開発や販売まで行っている会社ですね。
ぼくのいるアパレル業界でも、最終工程で、洋服に針が入っていないかどうかを確かめるために、
検針機に服を通して確認していますが、その検針機などを作っている会社ですね。へー、そうなんだ!
購入根拠
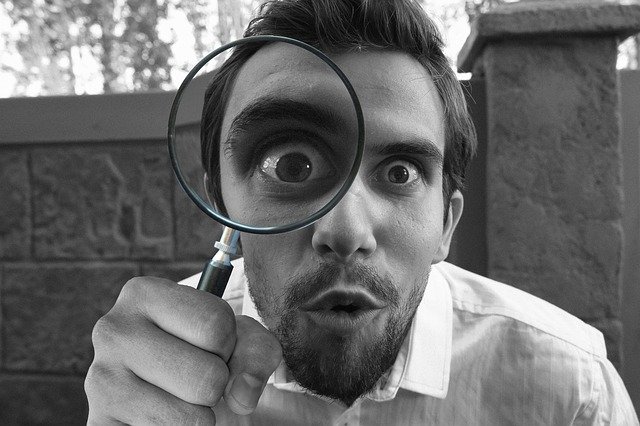
基本的な流れは、以下です。
四季報での銘柄探し
↓
テクニカル分析
↓
ファンダメンタル分析
↓
購入
では、順を追ってみていきましょう。
四季報から銘柄を見つける
売上・利益(百万単位) ※2020年 秋号
21.3予 【売上】115,000 【経常利益】18,000
22.3予 【売上】118,000 【経常利益】18,500
伸び率としては、あまり角度は高くないのですが、引き続き堅調な様子。
業界的には、5Gなどの追い風もあり、まだまだ伸びていくと予想しました。
また、財務指標等も、問題なさそうでしたので、手札銘柄に入りました。
四季報の詳しい見方については、以下をご覧ください。
さらに詳しく学びたい方は、こちらをおすすめしています。
テクニカル分析


・トレンドライン
前回同様、コロナの大きな下げにより、トレンドラインは使用不可です。
トレンドラインがわからない方は、以下の記事を参考にしてください。
・MA移動平均線
今回注目したポイントはこれです。
コロナショックの部分は大きく下落していますが、
全体的に見ると、綺麗な右肩上がりのチャートであり、
MA線もやや意識してされて、52週線で反撥している箇所がいくつかあります。
MA移動平均線がわからない方は、以下の記事を参考にしてください。
・レジサポ転換線
サポートラインは今回2か所引きました
一つは、いくつかレジストポイントになってる部分を結んだ平行線
一つは、直近の安値の出っ張り2か所を結んだ平行線
これらを損切ラインの基準として設定
・リスクリワードの設定
1.5:1で設定
利確の目標 : 2,660円(利回り 13%)
損切ライン : 2,150円(利回り -8.7%)
今回は、利確までの伸びしろが少なかったため、
上記のリスクリワードの設定となっています(通常は2:1の設定をしています)
利幅は少ないのですが、堅調な株価推移のため、手堅く着地できるのではないかと想定しました。
リスクリワードについては、以下の記事を参考にしてください。
株式投資は最悪どのくらい損するのか【 リスクとの付き合い方】
・その他
特に無しです、、、
ファンダメンタル的にはどうか
通信系は、5Gをはじめ、これからも伸びていくでしょうから、
間接的にアンリツも、業界の見通しは明るいのではと思っていました。
決算短信を見ると、やはり5G関連の事業が好成績で業績UPしており、
特に利益率が大きく増加していました。もともとかなり高い経常利益率に加え、
さらに収益性が高まるということで、期待はできそうと判断しました。
売買結果


・購入株数 : 100株
・購入金額 : 2,354円
・売却金額 : 2,710円
・利益額 : 35,600円(税引き前)
・利回り : 15.1%(税引き前)
・購入日 : 12.9
・売却日 : 1.21
・売買期間 : 43日
想定通りの値動きをしてくれ、設定額よりもう少し上を目指せそうな勢いだったので、
やや待った結果、目標よりもやや高い値段で売却に至りました。
伸び代があまりないチャートであったため、早い期間で売却までいけたこと、
また決算前に取引を終えられたことも、良いポイントでした。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
このような全体的にゆるやかに上昇しているチャートの波に乗ることも、アリと思えたトレードでした。
利幅が狭いですが、手堅く攻めることができる方法の一つになればと思います。
この場合、直近安値などの損切ポイントが重要になると思うので、
売買タイミングで、損失許容額とリスクリワードが適切に設定できるようであれば、
今後もこのような売買を増やしていきたいと思います。
銘柄選びの流れの基礎を知りたい方は、以下の記事をご参考にしてください。